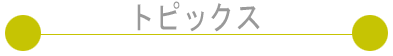- 9月6日衆議院総務委員会において、片山虎之助総務大臣は国家公務員の「退職手当引下げの行動を起こす」と述べ、来年度から支給率を引下げる意向を正式表明し、次期通常国会に退職手当法改正案を提出することを明らかにした。報道によればその削減幅は10%程度とされ、その影響はきわめて大きいもので、国家公務員労働者の将来の不安を抱かせ、老後の不安をいっそう掻き立てるものとなり断じて認めるわけにはいかない。しかも、本年の人事院勧告による本俸切り下げという人勧史上初の賃下げと軌を一つにしていることで、国家公務員の生活を脅かす暴挙と言わざるを得ない。実施されれば職員の士気と能率への影響は避けられない。
- 現在、国家公務員はスト権をはじめ労働基本権を制約されており、こうした条件下において、退職手当という直接的労働条件、雇用保障の根幹に触れる一方的改変は絶対に許されないものである。労働組合の合意なしの法案提出、審議、施行・実施は認められない。
- 総務省は「民間企業退職金実態調査」を実施しているが、その結果が明らかにされないままに総務大臣が「削減」発言を次々とし続けてきたことはきわめて重大であり、政治的であり、これらの発言は担当大臣として不誠実、不適切であることを指摘する。
- そもそも国家公務員の退職手当の水準について官民比較を単純に行うこと自体問題がある。国家公務員の退職手当制度は公務員特有の制約があり、民間とは異なる。民間の退職金制度は企業によりバラつきが多い上、加算金制度や算定基準に含めない「第2基本給」の存在、役員加算の非公開、そして企業年金による分割払い等々があり、比較そのものに無理が伴うものである。したがって官民比較による退職手当削減は「削減のための削減」になりかねず、慎重に取り扱われるべきものである。
- 今般の退職手当削減議論は、「天下り」廃止を求める国民の声に端を発している。キャリア官僚の退職金が7000万円にもなるといった高額の退職金を問題にしたものであったはずであり、いつしかすべての国家公務員の退職金を削減するものにすりかえられた。これは、それほどまでの高額の退職金を受け取れるはずのないわれわれ一般公務員へのしわ寄せであると言わざるを得ない。このような一律削減は、断じて認められるものでない。
|