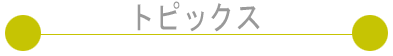- 【概要】
- 1月12日
・ 税研中央推進委員会大野亙事務局長が基調報告をしました。
・ 全国税税研中央推進委員会飯島健夫顧問が、「情報公開の取組み―税務行政に関して―」と題して特別報告しました。
・ 大阪市立大学大学院加茂利男教授が、「小泉構造改革を斬る―新しい国・地方財政関係をめざして」と題して講演しました。
- 1月13日
・分科会で熱心な討議が行われました。
- 1月14日
・ 金沢大学横山寿一教授が、「社会保障の構造改革と財源問題」と題して講演しました。
- 集会は、小泉「構造改革」は、国民に痛みの内容を知られないよう「常識」という言葉を巧みに使いながら進められていることを分析しました。
- 集会は、経済戦略会議の「日本再生への戦略」や経済財政諮問会議の「骨太の方針」等の政策が、グローバル化や規制緩和等により大企業の一部に富が一極集中しつつあることを分析しました。
- 集会は、政府・与党の経済財政政策は「失政」のつけを国民に押しつけていることを分析し、国と地方の長期債務残高は2002年度末で693兆円の見込みであることを明らかにしました。
- 集会は、多くの国民が失業、医療制度改悪など将来不安、逆進的な消費税・社会保険料負担に苦しんでいることが明らかにしました
- 集会は、小泉首相の「聖域なき構造改革」は、所得税課税最低限見直し、消費税増税など「大衆課税の強化」をおし進めようとしていることを分析しました。
- 集会は、新たな日本の国の姿として「テロへの対置」等を看板に有事法制づくりが進められていることを分析する一方、多くの国民が基本的な人権が尊重される平和な国づくりの道を望んでいることを明らかにしました。
- 集会は、小泉「構造改革」に対置する方向は、平和、福祉、雇用、教育など国民本位の理念が必要であることを明らかにしました。
- 集会は、社会的に大きな影響力をもつ大企業・高額所得者・大資産家の権益を規制し、その力を社会のために生かし、負担を求めることが必要であることを分析しました。
- 税制一般分科会は、政府・与党の推進する税制改革の結果、貧富の格差拡大を招いていることを分析し、税制における応能負担原則の徹底、所得再分配機能の強化等が、今、要請されていることを検討しました。そのためには、所得課税における課税最低限見直し、給与所得控除等のあり方を国民本位の立場で検討していくことが必要です。
- 暮らしと税金分科会は、「新自由主義」に基づく「骨太の方針」等により策定されている国の予算を分析しました。さらに、社会保障等の国民生活関連分野の改悪が進んでいる現状に対置する「第三の道」のあり方等を検討しました。
- 税務行政分科会は、情報公開、実績評価、公務員制度改革、国税庁「危機管理」、KSKシステム全国移行、電子申告導入等々、税務行政が大きな転換期にあることを分析しました。分散会方式により、最近の税務行政の問題点、確定申告書様式変更に伴う事務手続、「適正手続」(納税者権利憲章)制定の課題、外国人の課税問題等を検討しました。
- 集会では、元札幌国税局長濱田常吉が脱税事件で逮捕された事件は、顧問先斡旋などを背景にした税務行政の構造的問題の現れであり、税務行政の民主化の必要を指摘する意見が多く出されました。税務行政において「危機管理」が強調されていますが、これまで、税務署の内部事務が軽視等しされてきたことのよる諸問題を解決する必要があるとする意見がありました。
- 集会では、公務員制度改革問題は、信賞必罰の人事システム導入により、税務行政の現場にノルマ主義を蔓延させ、国民、納税者、職員に大きな矛盾をひき起こしかねない危険があることが分析されました。
- 以上のとおり、今集会の成果が今後、各地、各分野において運動推進の一助になることを期待するとともに、北陸の地で開催された今集会が関係者の奮闘により成功を収めたことを確認しました。
|